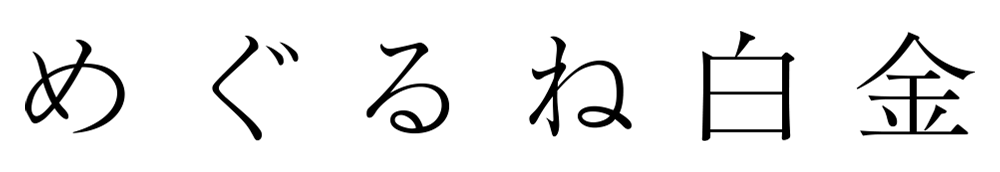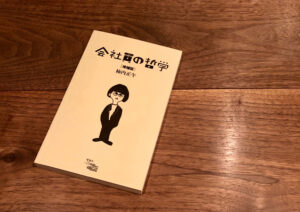正月休みで気が抜けてしまったのか、新年早々体調を崩した。一年の計は元旦にありというが、当初計画に我が身の不調までは盛り込んでおらず、まさかの事態に早速プランBを練り直す羽目に。開幕スタートダッシュに失敗し、その遅れを取り戻すこともなく体調回復と入れ替わるように訪れた大寒波の前に立ち尽くしている間に一月が終わってしまった。
寒さが厳しくなったのか自身の代謝が衰えたのか(前者であってほしい)、いずれにせよ身を突き刺す寒風の前になすすべもなく、ブックバーひつじがの営業が始まる前の時間に近所を彷徨く機会はグッと減った。その代わり、炬燵の中で丸まる時間が増えた。そう、この炬燵が良くない。昨年の秋に「使ってないけど使うなら送ろうか?」との悪魔の囁きに首を縦に振ったことにより実家から召喚された代物。我が家に到着後すでに多くの時間をこれによって溶かされていて、今となっては布団から這い出し電源を入れるまでが日々の習慣。こんな習慣ばかり労せず身につくのが悔しい。少しずつ温もりを帯びていくのを足先からじんわり感じつつ、テーブルの上に置いてある本をぱらりぱらりと読む。快適極まりない。床に腰掛ける状態で下半身だけを温めていたはずが、気がつけば肩までしっかり潜り込んでいて、もはや亀。うつらうつらしている間に開店の時間が迫り、今生の別れかのように名残を惜しみながら炬燵から現実へと旅立つ。毎日とまではいかないが、そうやって過ごす日が増えた。セルフ速度制限。春よ来い。早く来い。

とはいえそうやって出歩かない日が何日か続くと、それはそれでなんだか勿体ないことをしているのではと何とも言えない後ろめたい気持ちに駆られてしまう。怠惰と貧乏性の共存ほど厄介なものはない。今日こそは出るぞ出るぞと意気込みながら、それでもやはり炬燵の包み込むような温もりの前には簡単にその決意もへし折られ、奥深くまで潜り込んで『うろん紀行』(わかしょ文庫)を読み、せめてもの外出気分を脳内で味わっている。
はじめて連載の話をいただいたのは二〇十九年六月のことだった。全身に力をみなぎらせ、肩をいからせて意気揚々と海芝浦へ向かった日の、灰色の空と湿気でまとまらない髪の毛がありありと思い出される。それから毎月どこかへ出かけ、本を読み、文章を書いた。連載の題材はあらかじめ十二回分定められていたわけではなく、作品も土地も思いついたときに決めていた。いま思い返すと無謀だったとしか言えないし、よく続いたものだなと赤面する。
(『うろん紀行』p198 あとがきより引用)
『うろん紀行』は出版レーベル「代わりに読む人」のWEBでの連載が単行本化されたもので、著者のわかしょ文庫さんが読んだ小説の舞台になった街やその作品から連想される場所に実際に足を運び、情景や出来事を取り上げた作品の引用を挟みながら紹介する紀行エッセイである。聖地巡礼、まで大袈裟な話ではないかも知れないが、小説を読みながら頭の中に浮かんだ場所に実際に行ってみようなどそれまで思ったことがなかったので、この本を初めて読んだときはまずその試みの素晴らしさに心が震え、次にそれまでの己の読書の浅さを痛感したことによる寒気でより強く身震いした。わかしょ文庫さんの書く文章の読み心地がよいのもあり、もう何度も手に取って読み返している。大江健三郎の『万延元年のフットボール』を片手にコストコへ繰り出す話(第九章)が特にお気に入り。
大江健三郎の『万延元年のフットボール』を読むのに最も適した場所はコストコなのではないか。ふと頭によぎった仮説が真実かどうか確かめることにした。わたしはコストコに行ったことがない。コストコはアメリカからやってきた、物を安く大量に購入できるスーパー。行ってみたい気はしていたものの、年会費がかかり足繁く通わないとお得にならないため、あきらめていた。だが仮説検証のためには行くしかない。わたしは使命感に燃えていた。
(『うろん紀行』p.111 第九章「産業道路」より引用)
過去一度でもコストコに足を踏み入れたことがある人間なら、この章を読んでいるうちに不思議とわかしょ文庫さんがコストコの中をあてもなく彷徨い、所在なくぽつんと佇む情景が浮かんでくるだろう。いるかもしれないわかしょ文庫さんの影を追ってコストコに行きたいほどである。そうか、これが巡礼か。この章に限らず、本の中に書かれている言葉のひとつひとつからわかしょ文庫さんの存在がじわじわと滲み出て、それを追えば追うほどにぼんやりと氏の輪郭が頭の中に浮かび上がってくる。ぱっと見は紀行もしくは読書日記だが、よくよく読んでいく内にそれが著者が己の手によって刻んだ「わかしょ文庫」という存在そのものの記録であったことを知る。
景色や本に導かれるようにして、ようやくたどり着いたのが第十二章だった。第十二章の文章は、わたしにとってのターニング・ポイントである。連載のなかの一章であることを越えて、わたしの心に深く根を張った。第十二章は言うなれば墓標のようなもので、その墓標には、それまでの臆病で挙動不審なわたしの名が刻まれているだろう。わたしはこの先何度もこの墓標に立ち帰るような気がしている。そのたびごとにわたし自身が色の異なる花を手向けることができるよう願っている。
(『うろん紀行』p199 あとがき より引用)
本を読んでいると、自宅の、それもぬくい炬燵の中にいながらにして世界中どこでも旅した気持ちになるし、ありとあらゆる人の話を聞いた気持ちになることがある。手軽に色々なものを追体験することができてすごく楽しい。それがわかっていてじゃあなぜわざわざ時間やお金をかけて外に出て、人に会うのか。それをしたところで結局どうなるのか。万人が諸手を挙げて納得するような答えは出せないが、それらの行動によってどの本にも描かれていないし、何をどれだけ読んでもわからない「自分」の輪郭みたいなものを見つけることができるのかもしれない。『うろん紀行』を読んでいると毎回そんなことを考えてしまう。この記事を書き終わったら街に出よう。

▷書籍情報
『うろん紀行』
著者:わかしょ文庫 Twitter(@wakasho_bunko)
出版社:代わりに読む人 Twitter(@kawariniyomuhit)
Text/シモダヨウヘイ
中央区白金で「ブックバーひつじが」を経営。2018年福岡に移住。買ったばかりの白い服に食べ物の汁をこぼすのが得意。利き手は左。胃が弱い。