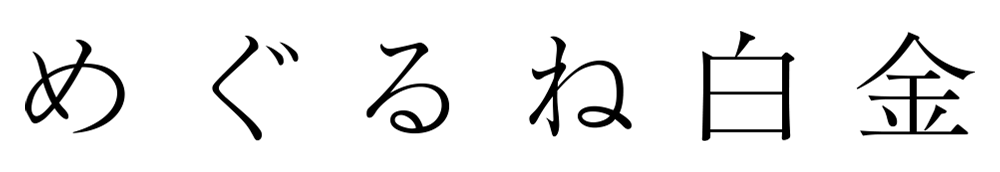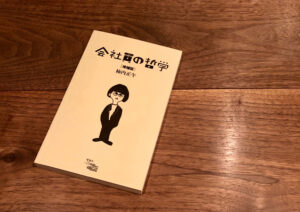暇があれば近くの本屋に行ってしまう。いや、暇がなくても気がついたら足がそちらのほうに向かっている。導かれている。読むべき本は家のそこらじゅうに積んでいるのに、行くたびに必ず新しい本が見つかるし、本屋からは何か不思議な磁力が発生しているとしか思えない。引き寄せられる何かが。
店(ブックバーひつじが)から程近いところにあるコトリノ・古書店も、そういう磁力を発生させている本屋のひとつ。大好きな場所だ。階段で3階まで上がって扉を開けると、そこはもう異世界。どことなく良い香りがする店内には、小鳥のさえずりが聴こえる。小説や絵本、雑学本などが壁一面に並んでいて、本棚の反対側にいる店主さんと背中越しに世間話をしながら手元に迎える一冊を選ぶ。どんな話題を持ちかけても小気味よく切り返してくれるのでありがたい。束の間の井戸端会議を楽しんだら、会計をして店に戻る。ひつじが営業前の定番の流れになっている。

コトリノ・古書店にはあらかじめ買う本を決めずに行くことの方が多い。それでも読みたい本がなくて困ったことがこれまでに一度もない。大型書店の棚で見落としてしまうような本が、いつだってふと視線に入る。これは規模が大きくない古書店だからこその発見だと思うし、それにしても毎回必ずと言っていいほど新しい本に出会えるので、コトリノ・古書店の選書はすさまじい。近くにそんな本屋があるのがうれしくって仕方がない。
コトリノ・古書店に限らず、ある程度小さい規模の本屋は棚の隅から隅まで眺めることができるのが良い。自ずと置かれている全ての本と目が合うし、限られた選書はその店の、そしてその店を営む人間の個性を如実に表していて、眺めているだけでもなんとなくどんな店なのかがわかってくるような気持ちになる。店主の顔が透けてみえる、そんな棚がある本屋が好きだ。
大阪にある梅田蔦屋書店で人文コンシェルジュをされている三砂慶明氏もそういう面白い棚を作られる、尊敬している書店員のひとり。選び抜かれた本が並ぶ棚からはじんわりと熱が放たれ、ついうっとりと眺めてしまう。彼がおすすめしている本は全部読みたいし、もしも家の近くにあったなら毎週新しい本を探しに通ってしまうはずだ。すごい棚。すごい書店員。
そんな三砂氏が編集で携わった書籍『本屋という仕事』には全国各地で同様に素敵な本棚を作っている書店員や個人書店の店主の声が並んでいる。本屋業界に関心がある人間ならまず聞いたことあるだろう贅沢な面々が、これまでどんなことを考えながら場を作り、保ってきたのか。そして日々どんなことを考えながら選書をし、棚を整えているのか。普段なかなか聞くことのできない裏側の話が盛り沢山で書かれていて面白い。一息に読み終えた後、なんだか無性に本屋に行きたくなり、その足でコトリノ・古書店へと駆け込んだ。何度も通ってもう見慣れた棚のはずなのに、改めて棚の隅々から熱がじんわり伝わってきて不思議だった。
どれほど苦境が続こうとも、私には、人間にとって本が不要になる時代がやってくるとは思えませんでした。その理由は、私たちの人生が言葉でできているからである。言葉は単独では存在しません。いつも誰かのためにあります。だから、一冊の本が与えてくれる驚きや発見、感動は読者の数だけ存在します。本と読書は一心同体であり、本屋とは読者と本との縁をつなぐ場所です。
(P.205「あとがき」より引用)
大なり小なりあれど、実店舗(リアル店舗)の場合そこに置ける本の冊数は限られている。有限であるからこそ、そこには選んだ人間の個性がより色濃く反映され、たとえそれで選ばれたのが同じ本であっても、その配置や組み合わせで与えられる印象の違いはもはや無限に近い。『本屋という仕事』を読むとどんな本棚にだって意図があることに気付かされる。そしてそれに気づいた状態で本屋に行くと、見慣れたはずの棚もなんだか違って見えてくる。本屋の磁力。その秘密に近づくためのヒントを教えてくれるような一冊で、その秘密の答えは本屋の中にある。
▷書籍情報
『本屋という仕事』
編者:三砂慶明 Twitter(@misagoyoshiaki)
発行:世界思想社
216ページ
Text/シモダヨウヘイ
中央区白金で「ブックバーひつじが」を経営。2018年福岡に移住。買ったばかりの白い服に食べ物の汁をこぼすのが得意。利き手は左。胃が弱い。